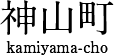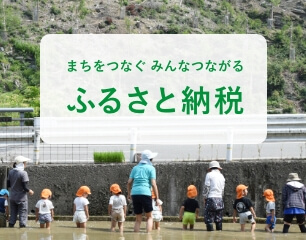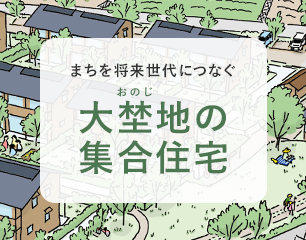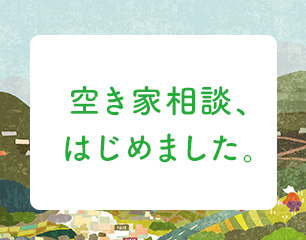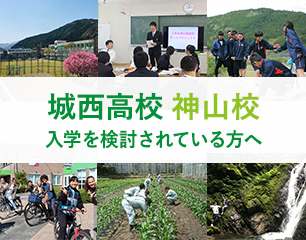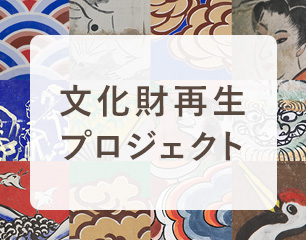外から町を見つめる。
―町外町民としての想い―
平成27年12月25日
東京を拠点に音楽・映像制作や舞台演出のお仕事を手がけられている南慎一さん。徳島市内出身ですが、神山にはお父さんの生家があり、幼い頃から頻繁に遊びに来られていました。その場所は、今では『WEEK神山』という宿泊施設になっていて、南さんが遊んでいた場所は新たな神山の交流の拠点になっています。外からの視点で神山町の変化をどう捉えられているか、お話を伺いました。
進歩した保守的
─今日は町外町民というか、そういう立ち位置でお話して頂ければいいかなと思っています。
南さん(以下:南) はい、町外町民。そうですね。
今でも帰省の際は必ず神山を訪れているんですけど、僕自身神山で生まれ育ったというわけではなくて、父の生まれ故郷なんです。
だから、ホントその幼少期の淡い思い出というか。
自分は徳島市内の住宅地で生まれ育ったので、神山は非日常のスポットでした。
農作業を手伝ったり、川で遊んだり、冬は焚き火をして焼き芋をする。
で、そうやってると、近所の人が挨拶に来てくれて、年に1回2回しか会わない人たちと一緒に焚き火を囲んで、みたいな。
そういう田舎特有の温かさみたいなのを感じてましたね。
だから今、自分の実家がWEEKになって、
東京や世界から色んな経営者やクリエイターの方が集っているっていうのが、
全く想像できないんですよね。
─ここまで注目されるようになった要因は何なんでしょうね。
南 神山の町自体の魅力というか、町が持ってるポテンシャルというか。
それがハードの部分じゃなくて、ソフトの部分のポテンシャルが大きいっていう所だと思います。
それは人の良さだったりとか、実際に移り住んでる人の人間性や人間力みたいなのもあると思うんですけど。
僕は神山の人っていうのは、基本は保守的だと思ってるんですよ。
けど、保守的なんだけども、限りなく進歩した保守的で。
─進歩した保守的。
南 多分新しいものが嫌いではなくて、抵抗あるけれども受け入れればものすごくやっぱりスピードが速いんじゃないんかなって気がしてて。
やっぱり住宅地とか、市内の方になると沈黙の干渉っていうのがあると思うんです。
声には出さないし、態度にも出さないんだけど、なんか干渉されてる感じというか。
神山はそうじゃなくて、チャレンジする人を応援する土壌があって、
何でも許してくれそうな雰囲気というか懐の深さみたいなのがある気がするんです。
普通だったら距離を置きそうなところも、ちゃんとこう馴染んでいくというか。
それはやっぱり神山の土地柄人柄なのかもしれないですね。
あとは、いい田舎加減なんじゃないかなあっていう感じはします。
基本はやっぱり不便だと思うんですよね。
不便だと思うんですけど、でもギリギリの不便さで生活が成り立っていて。
それは市内へのアクセスのしやすさだったりとか、コンビニも商店もあるっていうところだったりとか。
そういうのがなんか絶妙にマッチしてるのかなっていう。
町の平熱を上げていく
南 今、自分はエンターテイメントの仕事をしています。
映像制作や音楽制作といったいわゆる広告的な制作物一般と、
あとは舞台やステージの演出、プランニングっていうことがメインの仕事です。
なので、お付き合いしているのは広告代理店さんや、大手のプロダクションさんです。
「神山に拠点を持てばいいじゃない」って言われたことがあるんですよね。
当初、田舎の家(現WEEK)をサテライトオフィスにすればいいじゃんって言われて。
物理的距離っていうのは精神的距離にも比例していて、
近い距離の人にやっぱり仕事が来て、遠くなると仕事が来にくいっていうのはやっぱりあるので、
どうしても拠点は東京になっちゃうんですよね。
パソコン一個で河原見ながら仕事をしてる人とかもいるわけですよね。
あー、なんか羨ましいなあって(笑)。
手に入れることに関しては貪欲にやるんだけど、手放すことを人はやらなくなるじゃないですか。
手なんか2本しかないのに、いくらでも掴めると思ってるんですよ。
いつの間にか摑んでるつもりが実は掴めてない、みたいな。
そういう空回りみたいな状態が僕らの年齢の人って多いのかもしれないですけど。
一から収集し直すと、もしかしたらものすごい化学変化が起きるんだろうなっていう。
それをまあ人に勧めつつ、自分がやれないっていう矛盾がですね、
説得力ねえなあって思うんですけど(笑)。
やっぱり何か恩返しができるようなことをしたいというか。
そういうきっかけで帰りたいなあっていう思いがあるんですね。
例えば、今、自分が関わってる東京で開催されているイベントとかを、
今後神山でやるとか。
神山でもこういうことができるんだ、っていう。
世界発信のイベントをやって、そこにたくさんの人を呼ぶっていうことにチャレンジしてみたいんです。
僕は、ディズニーランドに人が行くような感覚で神山に人が集まることができればいいな、と思うんですよね。時々無性に行きたくなるときありません?
漠然とですが、お土産以外にも必ず心が満たされて帰るじゃないですか。
観光資源とかそういうことではなくて、ホント興味本位で神山に人がいっぱい来るっていうのが一番良くて、何かスキームや行く為に理由が必要とかそういうことではないと思います。
たまたまじゃあ今日時間あるから神山行こか、みたいな。
それは温泉に行くのでもいいし、ご飯を食べに行くだけでもいいし、
もしかしたら日常的に何かイベントとかワークショップをやってたりとか。
なんというか、平熱が高いイメージです。
だから、例えば僕が神山に関わるとしたら、町の平熱を上げる感じで関わりたいんです。
やっぱり打ち上げ花火的なコンテンツをやったりとか、カンフル作用を起こすのは違うと思うんですよね。
瞬間的に熱が上がると、その分冷めていくのも速いじゃないですか。
やっぱりじわじわと、体質改善をしていくじゃないですけど平熱を上げていくっていうのは、
5年10年、下手したら30年50年かかる話になるのかもしれない。
でも、そのほうが結果的に地域力が上がっていくと思います。
ニュートラルな場所であり続ける
─町外町民の方たちはどういうふうな形で町に関わるのがいいのでしょうか?
南 やっぱり、そういうきっかけっていうのは自然発生はしないと思うんですよね。
その為に、企画物でもプロジェクトでもいいけど、なにかは必要だと思います。
多分ね、誰しも目の前のことにいっぱいいっぱいで、
神山って何やってるんだろうなって思うほど余裕がないんですよ。
それに、若い人は別かもしれないけれど、
やっぱり30代後半から40代にかけての人たちってそこそこ中堅になってきてますよね。
そうやって腰を据えてやってる人たちが腰を上げて、
何かにチャレンジしようっていうのは、それだけのエネルギーが必要だと思うんです。
きっと、そういう自分を掻き立てる理由がないかぎり関わらない。
だから、なんか分からんけどむっちゃ面白そうやっていう動機付けが必要ですよね。
ただ、最近の神山は若者でなければ「何者であるか」を求められる場所だっていうのも事実だと思うんです。
なんか自分に武器がないとそこにいちゃいけないっていうか。
それって一つの会員制のクラブみたいで、よくないと思うんですよね。
ものすごく入口を狭めてしまうんで。
きっとそういうんじゃなくて、
もっとニュートラルで気張らなくても心地よい場所になれればいいいなと思うんですよね。
─少し敷居が高くなっているのかもしれない。
南 そう。
Uターンする人って、
一概にはいえないですけど、
都会の生活で何かしらの虚無感とか、壁にぶち当たってるわけじゃないですか。
そこで地元が、おいでよ! っていうスタンスじゃなくて、
で、君は何やってんの? っていうふうになると余計に疎外感があるというか。
やっぱり自分のふるさとのいいところっていうのは、
錦の旗であろうが白旗であろうが、とにかく迎えて入れてくれるっていう許容力だと思うんです。
神山ペース
南 今、神山自体が一つの岐路に立ってると思うんですよ。
それをいい方向にシフトしていかないと、町にとってもブレーキになっちゃう気がしています。
それは神山に限らず、どこもそうなのかもしれないけれど。
神山に足を向けられない理由があるのだとすれば、
やっぱり成功しなきゃいけないとか役に立たなきゃという思いなど、
神山のベクトルと合わせなきゃいけない気負いみたいなものだと思います。
代名詞になっているITとアート以外の看板にプラスして、
さらにもう一枚二枚立てられれば、広がりが出るのではと思います。
最近は食の分野などでも話題になってきてますよね。
そういう専門的な分野の他に、地域性を生かした日常的文化は人の幅を広げられるのでは。
僕は神山には、歩幅を変えないでほしいんです。
今、地方創生の一つのモデルとして周囲からの期待値が上がってます。
そうすると必然的に、もっと進化しなきゃ、歩幅を広げなきゃっていう焦りみたいなのが出てくるのかもしれないんですけど。
そうじゃなくて、マイペースというか神山ペースで、
今までの歩幅でゆっくりと進化して、熟成していってほしい。
とにかく何でもできるし、何でも応援してくれるっていうような安全地帯のような場所。
そして、30年後にものすごく人口減少がすごいことになっていたとしても、
何故かやっぱり元気な町であり続けてもらいたいです。