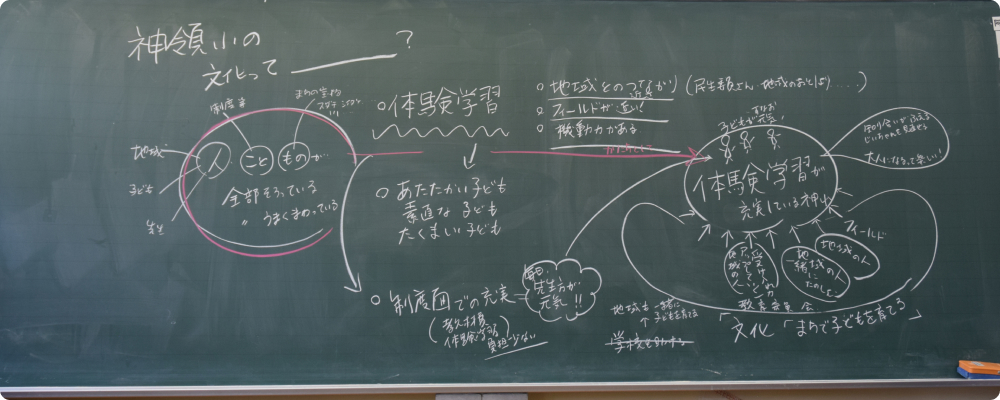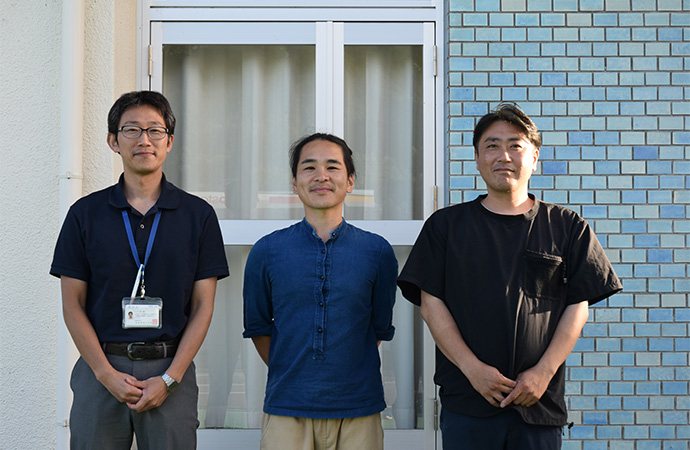06 神山で子育てをしている6人の保護者に、地域や
小中学校、高校進学についてまで伺いました。
神山町には、地元出身の家族、移り住んできた家族、さまざまな背景の子どもたちが住んでいます。阿波弁、東京弁、関西弁から英語など多様な言葉が飛び交っています。とはいえ、保護者たちは、同じまちで同じ時期に共に子どもを育て、見守る輪を自然と作っています。今回のインタビューでは、日程の都合でお父さん組3人、お母さん組3人といった形でお話を伺い、同じテーマごとにみなさんのお考えをピックアップしました。
お父さん組は、高校生以上のお子さんがいる町出身の坂井義隆さんと大家稔喜さん、町外から移り住み、神山で結婚して小学生など3人のお子さんがいる神先岳史さん。
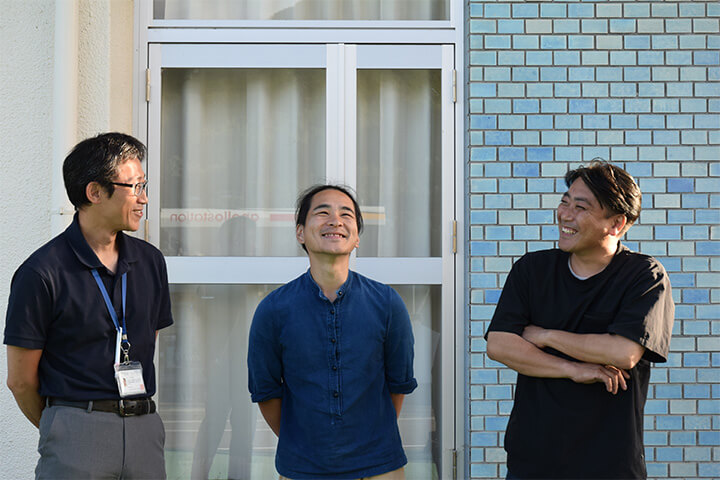
お母さん組は、パートナーが町内出身で結婚後に町に住み始めて26年の阿部三代さんと、ご夫婦とも町外出身の野原奈津美さん、農業をするために移り住み、小学校でも食農教育をサポートする松本絵美さん。野原さんと松本さんはいずれも小学生以下のお子さんがいます。

<神山という地域性>
「まち全体で子どもを育てていく神山」という言葉が生まれるほど、神山は子育てをしやすいまちです。実際に住んでいる方はどんなふうに感じているのでしょう。
松本:以前、大阪ではマンションに住んでいましたが、上下階、左右お隣さんに子供の騒音で迷惑をかけないか気を遣っていました。電車で移動する際も、車内でうるさくしないようにと緊張して乗っていましたね。なのに、神山に引っ越してきた時には、お隣さんから「この地域で子どもの声がするのがひさしぶりで嬉しい。どんだけ騒いでくれてもいいよ」と言われたんです。びっくりしました。「子どもの存在があるだけで、いいんだ」と思って楽になり安心しました。
昨年、鬼籠野神社の子どもの太鼓が何十年かぶりに復活したんです。長女が参加したら、地域の方から「こういうのができて嬉しいわぁ。ありがとう」と言われました。すごく嬉しかったですね。

鬼籠野神社でのお祭りの様子
阿部:うちの子どもは大きくなっていますが、神山のことが好きなので、夏休みなどに大学の友達を連れて、神山に帰ってきます。帰ってきて、川で泳いでいます。娘は神山のことを誇らしく思っているから、友達を連れてくるんだと思います。都会の子は自然に憧れるようで、1回来た友達はまた「来たい」と言ってくれています。
松本:確かに神山で育ったら、まちへの愛着は湧きやすいと思います。学校だけでなく地域の中でも、うちの子のことをよく知っていて、受け入れてくれる人がたくさんいるから。
<神山町の教育で、先生との距離感>
神山町の保育・教育は少人数が特徴の一つ。先生と保護者との関係性はどういった感じでなのでしょうか。
松本: 学校では、先生の目も行き届いているのがわかるし、他の子どもたちの親の顔もわかる。みんなが子どものことを見てくれているな、と思います。
阿部:兄弟や親子で揃ってみてもらえることも多いかもしれませんね。うちの子どもたちは6歳差でしたが、同じ先生が娘の時は担任、息子の時は副担任として受け持ってくれたんです。息子が日記に「祖父がお寿司を作ってくれた」と書いて提出したら、先生が「お姉ちゃんも、中学校の時に日記に書いてたわ」と教えてくれました(笑)。
野原:人数が少ないから、一人一人に目が届くんですよね。先生方が、全学年の子どもたちのことをよくわかっているくらい、目が届いていると思います。だから臨機応変に対応してくれる。大きい学校だったらできないけれど、校長先生にも、直接、話してみようと思える距離感がいいと思っています。

坂井:学校だけでなく学童でも同じ。学童に迎えに行った時に先生が、「子どもたち同士でこんな話をしていたよ」と情報をもらえるのが嬉しかったですね。関係が密だからこそできることですね。
坂井:地元出身だと、自分の子ども時代の先輩・後輩が、先生になって神山の小学校・中学校で担任の先生をやってくれることも多々あります。自分が担任として教えてもらった先生が、子どもの校長先生になって戻ってきたり、一旦退職されて再任用されて、子どもの学校でまたお世話になったり。
大家:公私の線はひくけど、安心ですね(笑)。愛着があるから、先生になっても神山に戻ってくる。でも、新しい先生も、水泳大会の見学など、親と話せる機会があると、その時にたくさん話をしてくれる。そういう関係は、いいなと思いますね。

<学校に関わる保護者、PTA活動>
少人数の学校で、先生との関係も密。そうなるとPTA活動については、みなさんどんな考えを持っているのでしょうか。
坂井:PTA活動は自分たちに取っては、子どもが通っているなら当たり前のことだと思っています。小学校は毎年、夏休みの間に、保護者が学校の掃除をしていました。コロナで無くなったけど、コロナ後は復活するかなと思っていましたが、そのまましない状態で行っていますね。準備も大変やけど、学校への関わりしろがなくなっていくのを感じますね。だから広野地区の夏祭りの前には、保護者の間で「会場になるから学校を掃除しないと」という話になったんです。来られる保護者だけで、自主的に掃除しました。
大家:最近はコロナが終わった後でも、運動会、餅つきといった学校でのイベントが簡略化されて寂しい感じになっています。運動会も1日開催していたのが、半日になって寂しい。
大家:毎年、奉仕作業はするものだと思っています。
神先:スケジュールを調整するのが難しいのですが、スケジュールが合えば行くという感じですね。僕は移住者ですが、それは覚悟して住みました。行ける人が集まっていて強制ではないというのなら、僕はマイナスの感情はありません。
<学校での食と農>
特に小学校は、「食」と「農」を間近に感じる学びのある環境です。どんなことを感じているでしょう。
野原:授業でも色々な体験をさせてもらっていますね。季節を通じて野菜づくり・収穫をして、かま屋へ卸し、さらにかま屋で、自分たちの野菜で作ってもらったランチを食べるという体験もあれば、椎茸組合に行ってしいたけのことを調べて、試食してというのもあります。うちの子は、家で学校の話をあまりしないんですが、体験授業の時は、自分から話してきますね。しいたけのことを調べに行った時に試食させてもらった「しいたけのカツ」が美味しかったようで「家でも作って欲しい」と言われて作りました。

「育てる、つくる、食べる」授業
https://www.in-kamiyama.jp/agriculture/monthy/45098/
神領小 学校だより
https://school.e-tokushima.or.jp/es_jinryou/news/1061361/
広野・神領小の取り組み
https://shokuno-edu.org/archives/1374
<子どもの放課後の過ごし方>
(見える化ページリンクhttps://www.town.kamiyama.lg.jp/child-rearing/education/after-school.html )
神山町は、まちの端から端まで、車で30分以上かかります。「友達と遊ぶ」が気楽にできない状態。子どもたちはどんな放課後を送っているのでしょう。
野原:放課後の過ごし方に選択肢があるところがいいなと思いますね。神領小は学校が終わった後、学童か鮎喰川コモン((神領小、神山中の近隣にある))という形で、子どもの行きたいところで選ぶこともできます。
神先:鮎喰川コモンでは、子ども同士が、いろいろな年齢の子どもたちが一緒に遊んでいるので、いいなぁと思いますね。同じ学年と遊ばずにお兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぶということもできる。
坂井:広野地区からはコモンへの移動手段が確保しにくいのが課題だと思っています。広野から子どもだけでは行けないから。広野は、多年齢の子どもが一堂に寄れる場所がないけど、(広野小の隣にある)「ほんのひろば」(https://honnohiroba.mystrikingly.com/)もある。ここは、すごくいいなぁと思っています。
大家:友達の家から友達の家まで10キロあるっていう環境は、なかなかないですね(笑)。小学校高学年以降には自転車で自由に行動できるようになるので行動範囲は広くなったけど、それまでは親の送迎がいる。
大家:夏は川で過ごすのが日常。プールが終わってから、また川に行くようなイメージです。だから「川に遊びに行く」という気合を入れた感覚はないですね。
松本:放課後子ども教室は、参加しやすいし、いつもと違う体験ができるなと。普段できないスポーツとか、関わることがないことに関わる機会があると嬉しい。
野原:習い事の選択肢が町内に少ないのは残念だと思っています。今、うちの子どもは、町外でグレイシーバッハという柔術を習っています。週2で通っていますが、ほんとうは週3回くらいは通わせてあげたい。でも、頻繁に通うにはちょっと遠いんですよね…。
坂井:町内でも移動に時間がかかるし、習い事は、親がどこまで送迎のサポートができるかという、距離的・時間的な問題は大きいですね。
(→町内の習い事ページリンクhttps://www.in-kamiyama.jp/diary/79212/)
<神山中学校、それから伝統行事、立志式>
神山中学校で50年以上、実施されてきた行事が毎年12月に行われている2年生の「立志式」です。2年生になると総合的な学習の時間「かみやまタイム」で地域の人との対話の場「おとなとしゃべり場」や「職場体験」などを体験。半年をかけて、自分の将来のあり方について考え、12月の立志式で「立志宣言」を行います。これについてどう感じているでしょう。
大家:最近の立志式には、感動しました。自分が中学生だった頃は、職業体験もなかったから昔の立志式とは、全然違う。今は、春からずっと立志式の準備をして、色々な体験をして、いっぱい考えてから立志式となる。子どもたちは、本当に真剣に取り組んでいるなぁと思います。
坂井:中学校2年生の時点で、「こういうふうになりたい」「こういうふうでありたい」というのをみんなの前で発表するという体験は、本人にとっても、保護者にとっても、すごく良いことだったなぁ、と思います。。

(立志式関連)
「まち全体で子どもを育んでいく神山」中学校の紹介
https://www.town.kamiyama.lg.jp/child-rearing/education/junior-high-school.html
2023年度中学校立志式
https://school.e-tokushima.or.jp/jh_kamiyama/news/1017559/
イン神山 立志式へ向けたキャリア学習授業など一覧
https://www.in-kamiyama.jp/?s=%E7%AB%8B%E5%BF%97%E5%BC%8F
<高校以上、進学のこと>
神山町内には、中学校を卒業後、神山校か神山まるごと高専、そのほかの高校を目指す場合は、町外を選択することになります。バス通学、寮生活についてはどう考えているのでしょうか。
阿部:昔は徳島市内の高校に行く子どもたちは、広野地域以外の子どもはほぼ全員が市内の寮に入っていたと思います。でも、最近はバス路線が増えたので、寮に入らなくてもバスで通える地域が増えましたね。バス通学する時も、町内では、徳島バスならどこでも乗降ができます。ただ、我が家からバスが走る道までは距離があるので、バス停まで祖父母が送り迎えしてくれました。ただ、バスは乗っている時間が長く、便数も少ないので、ほぼ送迎でした。息子はほとんどバスに乗っていません。部活や塾で遅くなる子は、家族が送迎したり、寮に入ったりしているようですね。
松本:寮生活だと自分で身の回りの事をするだろうし、生きる力がつきそうですね。私は、子どもは早くから自立するのがいいと思っているので、高校は子どもの好きなところであれば、徳島県内じゃなくてもいいかなと思っています。
神先:僕は子どもが家を出るのは、早ければ早い方がいい気がしています。小学校までは、生活や教育面で親が伝えられることがたくさんあると思うけど、中学校以降は自立心が芽生えてくると思うので、親離れ、子離れという観点も含めそう思います。
大家:子どもの進学にあたってはどんな条件も全力で支えると言う気持ちでいます。子どもの通う市内の高校は午前8時20分に始業ですが、神山からバス通学だと、遅刻してしまうんです。定期券は徳島市内まで、3ヶ月定期で50000円ちょっと。町の高校通学のバス定期代の補助を使うと半額になるんですが。神山町は、立地条件はええのに、バスの便が少ない。
坂井:「親に送ってもらわないと学校にたどり着けない」というのが、神山町に限らず、徳島県の中山間地域の課題やと思っています。高校へは、バス通学よりも下宿して自転車で高校へ行くパターンが楽だと思います。自分が高校生だった時も、下宿を始めた時、成長したなぁって感じました。
<まちの子育て制度>
神山町は、早くから子育て支援策を充実させてきました。年々、充実度が増していくプロセスの中で、子育てしてきた保護者はどんなことを感じていたのでしょう。
阿部:神山は、子育て支援策は、最先端を行っているような気がします。今は医療費無料も保育所無料も広がっていると思いますが、すごく早い時期からやっていましたね。今はもう大学1年生になっている息子が保育所に通って2年目ぐらいに、2人目からは保育料無料になりました。その時はびっくりしましたね。何年間も保育所に通ったのに、保育料を全く払わなくてもいいなんて。
医療費は、娘が成長するにつれて「医療費無料」の年齢が引き上がっていったんですよ。高校卒業するまで医療費を払わないで済むってすごい。窓口で1円もお金を払う必要がないんですよ。町外の病院に連れて行ったら、神山町の医療制度が知られていない時期で驚かれたことが何回かありましたね。今は給食費とか学校の教材費とかも、町が出してくれるでしょ?すごいですよね。
→「まち全体で子どもを育んでいく神山」子育て助成金ページへリンク
https://www.town.kamiyama.lg.jp/child-rearing/support/
「神山での子育て」当事者インタビュー
神山町で子育で教育に関わる人たちにインタビュー